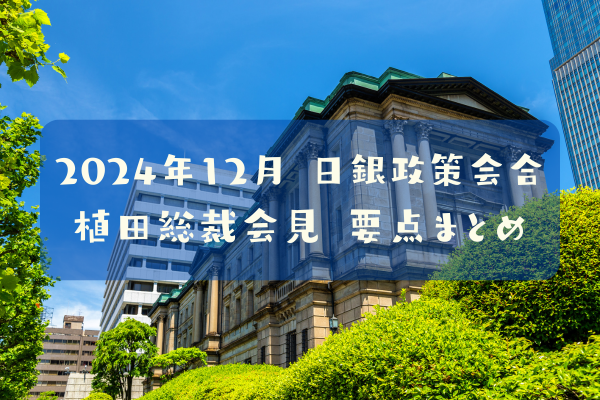
こんにちは、かりんです🥰
2024年12月19日(木)に行われた日銀金融政策決定会合(その後の植田総裁の会見)についてまとめます。
2024年12月19日(木) 日銀政策決定会合 要点
・無担保コールレート(オーバーナイト物)を、0.25%程度で推移するよう促す。
今回も市場の予想通りですが、全員一致ではなくた【賛成8反対1】での決定だったようです。
賛成:植田委員、氷見野委員、内田委員、安達委員、中村委員、野口委員、中川委員、高田委員。
反対:田村委員。田村委員は、経済・物価が見通しに沿って推移する中、物価上振れリスクが膨らんでいるとして、無担保コールレート(オーバーナイト物)を0.5%程度で推移するよう促すとする議案を提出し、反対多数で否決された。
当面の金融政策運営について 一部抜粋
わが国の景気は、一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している。海外経済は、総じてみれば緩やかに成長している。輸出や鉱工業生産は横ばい圏内の動きとなっている。企業収益は改善傾向にあり、業況感は良好な水準を維持している。こうしたもとで、設備投資は緩やかな増加傾向にある。雇用・所得環境は緩やかに改善している。個人消費は、物価上昇の影響などがみられるものの、緩やかな増加基調にある。住宅投資は弱めの動きとなっている。公共投資は横ばい圏内の動きとなっている。わが国の金融環境は、緩和した状態にある。物価面では、消費者物価(除く生鮮食品)の前年比をみると、既往の輸入物価上昇を起点とする価格転嫁の影響は減衰してきているものの、賃金上昇等を受けたサービス価格の緩やかな上昇が続くもとで、足もとは2%台前半となっている。予想物価上昇率は、緩やかに上昇している。
先行きのわが国経済を展望すると、海外経済が緩やかな成長を続けるもとで、緩和的な金融環境などを背景に、所得から支出への前向きの循環メカニズムが徐々に強まることから、潜在成長率を上回る成長を続けると考えられる。消費者物価(除く生鮮食品)については、既往の輸入物価上昇を起点とする価格転嫁の影響が減衰する一方、その基調的な上昇率は、マクロ的な需給ギャップの改善に加え、賃金と物価の好循環が引き続き強まり中長期的な予想物価上昇率が上昇していくことから、徐々に高まっていくと予想され、「展望レポート」の見通し期間後半には「物価安定の目標」と概ね整合的な水準で推移すると考えられる。なお、来年度にかけて
は、消費者物価(除く生鮮食品)の前年比に対して、政府による施策の反動が押し上げ方向で、既往の原油等の資源価格下落の影響などが押し下げ方向で、それぞれ作用すると見込まれる。
リスク要因をみると、海外の経済・物価動向、資源価格の動向、企業の賃金・価格設定行動など、わが国経済・物価を巡る不確実性は引き続き高い。そのもとで、金融・為替市場の動向やそのわが国経済・物価への影響を、十分注視する必要がある。とくに、このところ、企業の賃金・価格設定行動が積極化するもとで、過去と比べると、為替の変動が物価に影響を及ぼしやすくなっている面がある。
本会合では、2023年4月以降実施してきた「金融政策の多角的レビュー」を取りまとめた。「多角的レビュー」では、過去 25 年間のわが国の経済・物価・金融情勢について振り返ったうえで、非伝統的な金融政策運営の効果と副作用を点検し、先行きの金融政策運営への含意を整理した。日本銀行は、本レビューの結果も活用しつつ、引き続き、2%の「物価安定の目標」のもとで、その持続的・安定的な実現という観点から、経済・物価・金融情勢に応じて適切に金融政策を運営していく。
2024年12月19日(木) 植田総裁による会見 質疑応答
続いて植田総裁の質疑応答についてざっくりと。聞き逃したのもあります。まぁ参考程度に。
今回利上げをしなかった理由として、賃上げのモメンタムについてはどう考えている?
現時点では情報が少ないので今回慎重な判断をした。なので今は回答を控える。
多角的レビューで「非伝統的な金融政策手段」は将来の政策運営でも排除しないとのことだが、今後の利用する場合は以前よりハードルが上がっているか?
非伝統的手段を今後利用するかもしれないが、今回のレビューで検討したような副作用を点検しつつ採用していく。それぞれの手段についてどうか、という回答は控える。
賃上げの動向とアメリカのトランプ次期大統領の政策運営は1月会合までにある程度わかると思ってる?
春闘についてもトランプ政権の政策についても相当長い期間みないと全体像は判明しない。
各会合ではその時点までのデータをベースに総合的に判断していく。
トランプ次期政権の政策は不確実性が高いが高関税政策が発動した場合、日銀の見通しにどう影響するか?
どの国のなににどれくらい関税がかけられるのかある程度わからないと答えようがない。
現時点では不透明ではっきりしたことは申し上げられない
今後、非伝統的な政策を利用せざるを得ない時、ここまでに得た教訓はあるのか?
いつそういう事態になるかわからないし、その時の金融・経済情勢次第で効果や副作用も変わってくるのでなんともいえないが、その時のためにさまざまな材料、データを提供できるようにしている。
金融政策の判断タイミングは裁量的要素を意識的に強めているのか?
ゆっくり進んでいる理由は基調的物価上昇率がゆっくりであるから、利上げのペースを長い期間のなかで進めている。
どのタイミングで利上げをするかという方程式があるわけではなく、その時点その時点で最善と思われる判断をせざるを得ない。結果的に裁量的判断になっているだけ。
金融機関の不祥事が目立っているが、総裁はどう思う?
具体的なことには踏み込まないが、信用の大事な金融機関で不祥事が発生したことは遺憾。
どういう懸念があれば追加利上げを後倒しにするか?
具体的な事例を挙げるのは難しいが、日銀が次の利上げの判断に至るにはもうワンノッチ欲しいなぁというところ。ワンノッチのなかに賃金上昇の持続性も入っている。それをみたいから来年の春闘もみたい。
次の利上げタイミングが遅れれば遅れるほど、後の利上げペースはあがるのか?
利上げのタイミングが遅れれば遅れるほど、その後のペースは速くならざるを得ないが、そういうことを加味したうえで毎回の政策判断をしている。
基調的物価上昇率、インフレ期待の動きがゆっくりであることが政策判断を慎重にする余裕を生んでいる。
トランプ新政権の不確実性は、日銀の見通しにとってマイナスの影響が大きいのか?それともプラスの影響が大きい見方なのか?
トランプ政権が関税政策を行ったときに、経済にマイナスの作用を及ぼすものなので結果的にインフレ率にマイナスの影響を及ぼすこともあるとは思うが、現時点では不透明な部分が多くなんとも申し上げにくい。
追加利上げの判断時期が近付いていると以前言っていたが、今も同じ認識か?
春闘のモメンタムについて次回会合までにある程度の情報は入るが、全体がわかるのは3月とかになる。どの時点で利上げの判断ができるかは、その他のデータと併せて総合的な判断となる。
直近で為替は円安に振れているが、為替が物価に及ぼすリスクは10月時点と比べてどうか?
現時点では対前年比でみた輸入物価の上昇率は落ち着いている。
今年は円のボラティリティが凄いが、円の信用が揺らぎつつあるのではないか?という声もあるが、総裁はどう思う?
円の信認が揺らいでボラが大きくなったとは思っていない。
日本の国力の低下と、円の信認の低下はどういう関係があるか?
日本は営業収支黒字を維持しており、黒字を続けている国の信頼が直ちに揺らぐことはないと考えている。
米国経済の不確実性についてだが、アメリカの次期政権が始まったらまた新たなリスクが出てくるのではないか?利上げの判断を待つことのメリットは?
結局いつまで待っても不確実性は消えないのではないかという指摘だと思うけど、そりゃそうだけど時間が経つとともに情報が入るので判断材料が増える。今は判断材料がなさすぎる。
今日は日米の株価が大きく下落したが、こういうことも日銀の利上げするかどうかの判断に影響するのか?
短期的な株価動向についてはコメントを控える。
ただ株価動向を含めさまざまな資産価格の動向は常に注視している。
市場では1月会合の利上げが織り込み始めている。そろそろ利上げしないリスクについても認識しているのか?
田村委員は物価に上振れリスクがあるということで利上げの提案をしたが、今日の時点では否決された。具体的な内容については数日後に発表される「主な意見」をみて。
以前の会合で時間的余裕という言葉を使ってたけど、また時間的余裕がある状況になってきているのか?
以前「時間的余裕」という言葉を使った際には、米国の景気下振れ懸念に由来する金融市場の不安定性を見極めていくということで使っていた。その紐づけがあまりに強くなりすぎた、ということと米国経済の下振れリスクが小さくなったので、前回会合で「時間的余裕」という表現を継続的に使うことをやめると言った。
だが「時間的余裕」というのは色々なことで使う言葉である。基調的物価上昇率がゆっくりしているときは、いろんなことを見極めていくことは可能である。
とりあえず今回はさまざまなリスクを見極めるために、利上げはせずに金利を据え置いた。
もう少し春闘のモメンタムをみたい、ということだったが1月になったら判断できるのか?
賃金について1月の会合でにどれくらいわかるか?というのは現時点では予想しがたい。
利上げの判断はその他のデータとの総合的判断でもある。
基調的物価上昇率がゆっくりなら、どこまでも利上げの判断を伸ばすことができるのか?
足元の動きがゆっくりであっても、強い緩和的な状況が長く続けば先行きどこかで急上昇するというリスクが常にあるし、利上げをしない判断はそのリスクを拡大させてしまう。そういうことを考えたうえで、各会合時点で利上げをする、しないの判断をしている。
2013年以降の大規模緩和は我が国にとってプラスだったと判断しているようだが、もし総裁がタイムマシンで2013年に戻ったら同じ政策をするのか?
それは将来同じようなケースになった時の判断にも通じるが、それはその時の情勢次第。
ただ大規模緩和のようなことは期待物価上昇率に与える効果は、思ったほど確実ではなく副作用もいろいろある。そういうことを考えつつ判断することになる。
日本経済の病状を教えてほしい。日本経済は急病からは回復したかもしれないが、慢性疾患のような状況なのではないか?
日銀が治療の対象にしたいと考えているのは、物価の安定性を取り戻すということ。それは2%のインフレ率の持続的安定的にすること。ほかの病気ももちろんあるが、金融政策の手段では効果が薄いと考えている。
日銀のコミュニケーションポリシーについて聞きたい
コミュニケーションの基本は、日銀の物価見通しや日銀の見通しを伝えていくということ。
日銀の金融政策の基本的考え方を丁寧に誤解が生じないように説明していくしかない。
景気があまり上がらずに供給制約により物価上昇率が上がった場合も利上げは選択肢になり得るのか?
単純なケースだが「人手不足」はある種の供給制約で、これが賃金上昇の一つの要因になっていることは否定できない。あるいは物価に影響も与えていることもある程度起こっているが、日銀としてはこういうことも考慮して場合によっては対応していく。
0.5%より先の利上げについてどう考えているか?7月の会見で0.5%は壁として意識していないとおっしゃっていたが、今もそうか?
0.5%という水準に特に意識はもっていないが、金利を引き上げていくにつれてより一層注意深く判断していかなくてはならなくなる。どこからがより慎重になるのかはその都度判断していく。
まとめ
まとめると、こんな感じかな😋
個人的に思ったのは「日銀が次の利上げの判断に至るにはもうワンノッチ欲しい」という表現は若干ハト派な印象ですかね。
今回は取り急ぎ以上です!
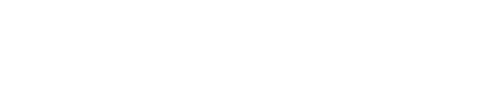






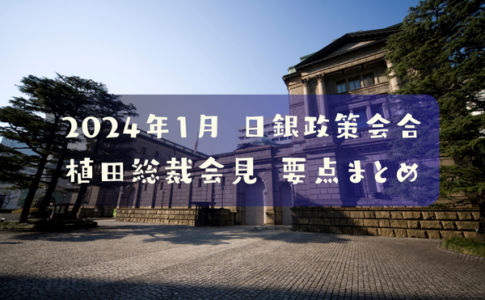





・春闘のモメンタムとアメリカの時期政権の政策をある程度みたい
・日銀が次の利上げの判断に至るにはもうワンノッチ欲しい
・基調的物価上昇率、インフレ期待の動きがゆっくりであることが政策判断を慎重にする余裕を生んでいる
・強い緩和的な状況が長く続けば先行きどこかで急上昇するというリスクが常にある
・0.5%という水準に特に意識はもっていない