
こんにちは、かりんです🥰
2025年03月19日(水)に行われた日銀金融政策決定会合(その後の植田総裁の会見)についてまとめます。
2025年03月19日(水) 日銀政策決定会合 要点
・無担保コールレート(オーバーナイト物)を、0.5%程度で推移するよう促す。
はい、現状維持です。今日は発表早かったですね、前場引け前に出るなんて。
まぁ、今回も事前に小出しで各種メディアから「据え置き濃厚か?!」と報じられていましたので、特にこれ自体にはサプライズはなしかと。
当面の金融政策運営について 一部抜粋
わが国の景気は、一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している。海外経済は、総じてみれば緩やかに成長している。輸出や鉱工業生産は横ばい圏内の動きとなっている。企業収益が改善傾向にあるもとで、設備投資は緩やかな増加傾向にある。雇用・所得環境は緩やかに改善している。個人消費は、物価上昇の影響などがみられるものの、緩やかな増加基調にある。住宅投資は弱めの動きとなっている。公共投資は横ばい圏内の動きとなっている。わが国の金融環境は、緩和した状態にある。物価面では、消費者物価(除く生鮮食品)の前年比をみると、既往の輸入物価上昇を起点とする価格転嫁の影響は減衰してきているものの、賃金上昇等を受けたサービス価格の緩やかな上昇が続くもとで、政府によるエネルギー負担緩和策の縮小もあって、足もとは3%台前半となっている。予想物価上昇率は、緩やかに上昇している。
先行きのわが国経済を展望すると、海外経済が緩やかな成長を続けるもとで、緩和的な金融環境などを背景に、所得から支出への前向きの循環メカニズムが徐々に強まることから、潜在成長率を上回る成長を続けると考えられる。消費者物価(除く生鮮食品)については、既往の輸入物価上昇を起点とする価格転嫁の影響が減衰する一方、その基調的な上昇率は、人手不足感が高まるもと、マクロ的な需給ギャップの改善に加え、賃金と物価の好循環が引き続き強まり中長期的な予想物価上昇率が上昇していくことから、徐々に高まっていくと予想され、「展望レポート」の見通し期間後半には「物価安定の目標」と概ね整合的な水準で推移すると考えられる。
なお、来年度にかけては、消費者物価(除く生鮮食品)の前年比に対して、米価格が高水準で推移すると見込まれることや政府による施策の反動が生じることが押し上げ方向で作用すると考えられる。
リスク要因をみると、各国の通商政策等の動きやその影響を受けた海外の経済・物価動向、資源価格の動向、企業の賃金・価格設定行動など、わが国経済・物価を巡る不確実性は引き続き高い。そのもとで、金融・為替市場の動向やそのわが国経済・物価への影響を、十分注視する必要がある。とくに、このところ、企業の賃金・価格設定行動が積極化するもとで、過去と比べると、為替の変動が物価に影響を及ぼしやすくなっている面がある。
2025年03月19日(水) 植田総裁による会見 質疑応答
では続いて植田総裁の質疑応答についてざっくりと。
聞き逃したのもあります。まぁ参考程度に。
今春闘の大規模な賃上げは今後の政策運営に与える影響は?
春闘の賃上げ率5.46%と昨年に引き続き高水準となった。大企業だけでなく、規模が小さな企業でも高めの賃上げ率が広がってきている。概ね日銀の見通しに沿ったものと評価している。
賃金動向は引き続き丁寧に注視する。
賃金だけでなく幅広く経済物価、金融情勢を点検し、物価見通し実現の確度に及ぼす影響を見極めていくことが重要と考えている。
足元の物価動向は高い伸びを示しているが、これは基調的物価の想定の範囲なのか?
消費者物価の上昇が国民負担をあげていることは認識している。政府によるエネルギー負担緩和策の縮小に加え、コメ価格の上昇が影響している。
これらの物価上昇は基調的な物価上昇率に二次的な影響を及ぼし得ると考えている。
そのうえで、現時点ではこの点を踏まえても、基調的物価上昇率はじょじょに高まってきているが、なお2%を下回っているという認識に変わりはない。
日銀としては経済物価に関するさまざまなデータをみて物価情勢を評価する。
トランプ政権が関税発動したら日銀は利上げできるの?
米国の関税政策は不確定なところが大きいとみている。
米国の関税政策が世界経済に及ぼす影響を見極めたうえで、我が国のインフレ、経済見通しにどういう影響を及ぼすか精査して、日銀の金融政策を決めていく方針に変わりはない。
異次元緩和から転換して約1年経つが、これまでは計画通りに進んできたのか?また今後の金融政策正常化のプロセスは?
少しずつ基調的物価上昇率が2%に収束する確度が高まるもとで、それに基づいた適切な緩和度合いの調整ができたと思っている。国債買い入れの減額も予定通り進んでいる。
今後、国債買い入れ減額について6月に中間評価を行う予定。基本は去年進めた計画に沿って進めるが必要があれば修正する。
ETFはもう少し時間をいただいて適切な処分の方法を考えたい。
国内要因の物価上振れリスク、海外要因の下振れリスクはどちらを重視する局面か?
国内・海外の両方をみて経済物価見通しに的確に反映させて政策を決めていく。
海外の不確実性は4月の初めにはある程度わかるのではないかなと思っている。
国内の賃金物価の好循環は、おおむねオントラック、オントラックのなかでも若干強め。
今日の会合でも一部の委員から物価の上振れリスクに注意したいという発言があったので、それも踏まえて両面を注視して政策に反映させていく。
今は基調的物価上昇率はどれくらいなのか?
日銀としてももう少し明確に示したいと考えているが、これを示せばみなさまに納得してもらえるというデータがあるわけではない。引き続き努力を続けてもう少し絞ることができれば適宜公表するが、まだその手前の段階。
私(植田総裁)がどれくらいとみているかというとはまぁ1%以上、2%は下回るという状況とみている。
トランプ大統領が円安誘導を批判している。日銀が金利を上げて円を強くしないと、関税をかけるぞと言っているようにも聞こえるが、植田総裁はこの発言どう思う?
トランプ大統領の発言についてはノーコメント。
経済物価見通しにそって政策を行うだけ。
1月に利上げをした時と比べて、追加利上げをするのが難しい状況になっている?
世界経済をめぐる不確実性は増している。
国内の賃金物価の好循環は順調。両方合わせて今後の見通しを的確につくりそれに応じて政策を行っていく。
中立金利の水準は?中立金利に近づく手ごたえがあまりない場合、利上げのペースを上げるのか?
中立金利は依然として絞り切れていないという点は変わっていない
金利を何回か上げてきているが、それによって経済物価の反応をみながら中立金利のあるべき場所を絞りつつ、その後の政策につなげていければ、と考えている。
今回の決定会合に金融機構局は出席したの?出たならその理由は?
(出席した、ということだと思う)
二つ理由があり、ひとつは金利をここまで上げてきているなかで、金融システムに影響が出ているかいないか?の議論を行うため。
もうひとつはマクロの議論?を金融機関に聞いてもらうことで、より充実した活動をしてもらえるのではないかという期待もある。
世界経済の不確実性が完全に晴れることはないと思うが、世界経済の影響が国内に及ぶ範囲が限定的、もしくは国内経済の見通しが堅調であれば利上げを続けるということか?
関税がかかることで経済物価に影響を与えるということはかなり先にならないとわからないが、政策や市場のマインドがどうなるかはある程度見通しがつく部分もあるので、手遅れにならないように政策を進めていく。
長期金利の上昇について要因と受け止めを教えて?
短期の動向についてはコメントを差し控えるが、ここしばらく上昇の傾向にあるということは承知している。1月から最近にかけてのインフレ率、GDPデータ、直近の賃金に関する動き、さらにドイツの金利の上昇などの動きに反応しているというのが、市場での見方と理解している。
これらを含めて長期金利は市場で形成されるものであると考えているが、通常の価格形成とは異なる形で金利が急上昇する例外的なケースには、市場における安定的な価格形成を促す観点から機動的なオペをすることもあり得ると去年の7月に決めた。
現状はそうした状況ではないと考えているが、引き続き市場を注視していく。
足元のコメの上昇率などは基調的物価上昇率には影響を与えない、ということ?
食品価格の上昇は、一時的なサプライショックであるとみるべきだが、こめ価格の上昇は若干長引いているし、インフレ期待、消費者マインドなどを通じて基調的な物価に影響を与える可能性もゼロではないので、その辺はしっかりみていく。
食品価格の上昇に対して、金融政策は直接影響する手段をもっているわけではないので、無理にでも下げる方向に動けば、食品だけでなく景気全体を冷やすことになる。それはあまりにもコストが大きい。(やらないということ)
日本経済はオントラックと本当に言えるのか?
第一四半期のGDP、日銀が発表している消費活動指数もちょっと弱いが、特殊要因として中国の春節が例年と違うところにきて、インバウンド消費が1月にきている。その分を引きすぎている部分も考えられる。そうしたことから予想されるほど悲観的にはみていない。経済が悪い時に無理して利上げをすることにはならない。
長期金利の上昇が日本経済に与える影響は?
長期の名目金利があがっているなかで、実質金利も少しずつマイナス幅を縮めている点について、日銀の見方としては経済活動に大きな影響があるのは短期から中期ゾーンの金利とみている。このゾーンはまだかなりのマイナスのところにある。イールドカーブ全体としては、経済活動をサポートするレベルにある、とみている。
基調的物価を重視しているのはわかるが、CPIは3年近く2%を超え続けているが後手に回っているビハインドザカーブのリスクはない、ということで変わりはないか?
消費者物価総合でみればCPIが2%を超えているのはおっしゃる通りで、国民生活へのマイナスの影響は強く意識している。日銀が目標としているのは、2%の物価目標を持続的に実現することなので、その点からみると、基調的物価上昇率は2を少し下回っているとみている。
サービス価格の上昇はそれほど強いものではない。普通の意味でのビハインドザカーブのリスクはそれほど高くはない。
今後、市場が荒れている場合は利上げはしないのか?少々荒れていても利上げを強いるのか?
確かに去年の8月9月ごろには米国の景気懸念から市場が大きく荒れたことがあり、その時は「これが収まるまでは」と申し上げた。その後は同様の趣旨のことを申し上げていない。現在はそういう状況ではないと考えているし、一般論としては程度の問題。
日銀が利上げを継続する場合、地域の金融機関の再編が促されるのではないか?と言われているが総裁はどう思う?
地域銀行同士が、合併・統合するというのは各銀行の判断で行うこと。金融政策で影響を与えようとして動くことはない。
今後、追加利上げをするうえで国内経済の重要なデータはあるか?
これまでと基本的には同じ。
春闘の一次集計は見通しの中でも強めのところに落ち着いた。
これが今後どれくらいの広がりを見せるかがまず一点。
それと賃金の強い動きが価格にどう転嫁されるかをみていく
春闘の動きの波及は、次回会合4月、5月くらいまでみれば判断できるのか?それとももう少し先になるのか?
中小企業ぜんぶみるとするとだいぶ先になるので、程度問題になる。
賃金だけでなく、そのほかのデータが強いかどうかなど総合的にみる。
コストプッシュのインフレ率が下がっていったとしても、家計のマインドや予想物価が上振れて利上げを早めるリスクはあるのか?
家計の予想インフレ率は食品があがると割とすぐにあがるパターンはあるので、もう少し中長期でのインフレ予想に広がりがあるかどうかを注視していく。
コメの価格上昇、家計のインフレ予想は日銀にとってはプラスだということか?
現状の見通し通りに推移すれば、見通し期間の後半には基調的物価も2%にだいたい到達するとみているので、ここから上振れをするのであれば緩和度合いの調整を早める可能性がある
長期金利の上昇がもたらす、6月の国債買い入れの減額計画の中間評価への影響はどうなる?
今後検討を本格化させる。
それまでの市場動向などを改めて点検して、これまでの計画通りに進めるのか、それとも修正が必要なのかを検討する。
基調的物価目標2%ってのは、総裁は正しいと思うか?
まず達成することが重要だと思っている。
そのうえで将来どこかの時点で、目標を修正することもなきにしもあらず。
次の政策金利0.75%という金利は、まだ緩和的であると言えるのか?
アメリカの関税政策がどんな程度のものにあるのかによる。
利上げはだいたい半年に一回くらいのペースなの?
今後の経済物価のデータ次第。
まとめ
今回はのらりくらりというか。特に印象的なのもなかった印象。
まぁまとめるとこんな感じ?
今回は取り急ぎ以上です!
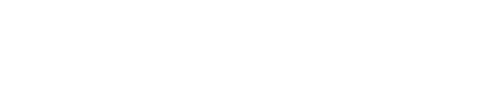


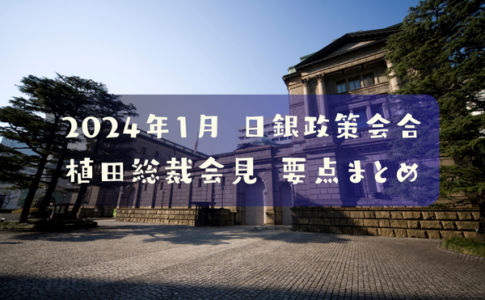









・国内の賃金物価の好循環はおおむねオントラック(オントラックのなかでも若干強め)
・米国の関税政策は不確実性が高い
・足元の物価動向が高い伸びとなっていることは認識している
・そのうえで基調的物価上昇率はなお2%は下回っているという認識
・海外の不確実性は4月の初めにはある程度わかるのではないかと思っている
・植田総裁は現状の基調的物価上昇率は「1%以上、2%は下回るという状況」とみている