
こんにちは、かりんです🥰
2025年05月01日(木)に行われた日銀金融政策決定会合後の植田総裁会見についてまとめます。
2025年05月01日(木) 日銀政策決定会合 要点
・無担保コールレート(オーバーナイト物)を、0.5%程度で推移するよう促す。
事前の予想通り、今回も現状維持です。
特にサプライズはなしかと。
展望レポート(概要)
・先行きのわが国経済を展望すると、各国の通商政策等の影響を受けて、海外経済が減速し、わが国企業の収益なども下押しされるもとで、緩和的な金融環境などが下支え要因として作用するものの、成長ペースは鈍化すると考えられる。その後については、海外経済が緩やかな成長経路に復していくもとで、成長率を高めていくと見込まれる。
・物価の先行きを展望すると、消費者物価(除く生鮮食品)の前年比は、2025年度に2%台前半となったあと、2026年度は1%台後半、2027年度は2%程度となると予想される。これまで物価上昇率を押し上げてきた既往の輸入物価上昇やこのところの米などの食料品価格上昇の影響は減衰していくと考えられる。この間、消費者物価の基調的な上昇率は、成長ペース鈍化などの影響を受けて伸び悩むものの、その後は、成長率が高まるもとで人手不足感が強まり、中長期的な予想物価上昇率が上昇していくことから、徐々に高まっていくと予想され、見通し期間後半には「物価安定の目標」と概ね整合的な水準で推移すると考えられる。
・2026年度までの見通しを前回の見通しと比べると、成長率については、2024年度は幾分上振れているが、2025年度と2026年度は、各国の通商政策等の影響を受けて、下振れている。消費者物価(除く生鮮食品)の前年比については、2025年度と2026年度は、原油価格の下落や今後の成長ペース下振れの影響などから、下振れている。
・リスク要因としては様々なものがあるが、とくに、各国の通商政策等の今後の展開やその影響を受けた海外の経済・物価動向を巡る不確実性はきわめて高く、その金融・為替市場やわが国経済・物価への影響については、十分注視する必要がある。
・リスクバランスをみると、経済の見通しについては、2025年度と2026年度は下振れリスクの方が大きい。物価の見通しについても、2025年度と2026年度は下振れリスクの方が大きい。
2025年05月01日(木) 植田総裁による会見 質疑応答
では続いて植田総裁の質疑応答についてざっくりと。
聞き逃したのもあります。まぁ参考程度に。
トランプ政権の関税政策について、現時点でどう分析している?
海外経済、日本経済の減速、先行きの不透明感など経済の下押し要因として評価している。
その後は海外経済が緩やかな成長経路に復していくことから、下押し要因は次第に弱まっていくとみている。
物価に対しては成長ペースの鈍化などを通じて押し下げ方向に作用するとみている。基調的な物価上昇率にもいったん伸び悩むことを想定しているが、その後は徐々に高まっていくと予想している。
物価安定の目標が概ね整合的な水準で推移するのは見通し期間の後半(26年度後半~27年度?)になるとみている。
見通し期間内に基調的物価上昇率が整合的水準まで高まるという見通しはこれまでと変わっていない。
各国の通商政策等の今後の展開やその影響をめぐる不確実性は高いと考えている。
物価安定の目標が見通し期間の後半に後ろ倒しになったのなら、利上げのタイミングもその分遅れるということか?
なかなか難しい問題。
これまでのように単調に基調的物価が上昇するというより、いったん足踏みするような見通しなので、そのあたりを柔軟に考えて政策運営するつもり。
中心的な見通しの確度は残念ながらこれまでほどは高くないとみている。
関税政策が将来的に金融政策の動向にも影響を与える可能性はある。
現時点で経済と物価はオントラックと言えるのか?
足元までは概ねオントラック。
米国の関税政策の交渉にこれから進展があるとはいえ、それでも無視できないレベルの関税が残ることを前提にした見通しになっている。
6月会合で国債買い入れの中間評価と26年度の減額計画を示すと思うが、経済の減速リスクを受けて景気を支えるために国債買い入れの減額ペースを緩めたり、止めたりすることはあるのか?
金融政策は短期金利の操作を主に行うことを考えている。
米国の関税政策はどの程度の想定で見通しを作っているか?
(総裁個人としては)これまで関税について議論されたなかで一番極端に高い結果にも低い結果にもならない想定。
基調的物価上昇が足踏みする、との発言があったが経済と物価の上昇タイミングがずれこみスタグフレーション的な状況にもなり得るか?
現時点では何とも言えない。
今後の関税政策の不確実性をある程度見極めできるのはいつごろか?
90日間の停止期間がひとつのポイントとなると思うが、その前段階の個別交渉が済む可能性もあるし、90日間経ってもまだわからないパターンも考えられる。
不確実性は大きいと考えている。
次、利上げをするのは相当程度先か?
今回の中心的な見通しに、どのように経済が沿って動いていくか。
見通しの確度がやや低い中で、関税政策などによって見通しの変更を迫られるケースもあるので、それ次第。
利上げの判断には賃上げが続くかどうかも重要だが、今年の冬のボーナスや来年の春闘もある程度見通せるまで利上げは待つのか?その前段階で利上げすることもあるのか?
賃金はひとつの重要な判断基準だが、賃金の先行きは(冬の手前の)企業収益などからある程度推しはかれるので待たないと利上げできないわけではない。賃金動向の大小だけで利上げの判断が決まるわけではない。
ETFの処分について、関税政策の影響で検討状況に変更はあるか?
ETFについては引き続き検討中。
基調的物価上昇率が2%の整合的な水準になるのが1年遅れたということで、利上げのペースは緩やかになるという市場の受け止めだが、総裁としては必ずしも利上げのペースは緩やかになるというわけではない、ということか?
基調物価が2%に到達する時期は後ろ倒しになったが、基調的物価のたどるであろう経路がやや複雑な見通しになったので、どこで利上げの判断をするのは難しいところ。
不確実性が高まり見通しが後ろ倒しされたのに、利上げの方向性は維持されているが、その理由は?
見通しが下方修正になったとはいえ、見通し期間内に基調的物価が2%に到達する見通しは維持されているから。
物価安定目標の到達時期は25年度、26年度、27年度の3年度の中の後半、つまり26年度の後半か27年度中のどこかという意味か?
おっしゃるとおりだが、今後のデータ次第で前倒しになったり後ろ倒しになったりする可能性はある。
展望レポートで見通しが下方修正されて、今まで以上に不確実性が高まっていてこれまでのオントラックとは変化したのか?不確実性が高まっていることで利下げの局面が早くくると考えてもいいのか?
足元までのデータはオントラックであった。
米国の関税政策があり将来の経済の影響を考えて見通しを変えたので、見通しを変えたばかりなので今後のデータを見てみないとわからない。今後も見通しが変わるかもしれない。そういうことが今後の金融政策に影響してくる可能性がある。
基調的物価上昇が足踏み状態に入るとのことだが、見通し実現の確度が高まっていると判断できれば利上げをする可能性はあるのか?
今日示した中心的な見通しに沿って経済が動いていくなかで、来年度後半くらいには2%に到達する見通しに自信がもてた段階で利上げをする可能性はある。
賃金と物価の好循環は総裁の幻想ではないか?
やや誤算だったのは去年のなかば過ぎから食品価格の上昇が目立ってきた点。これは第一の力がまたでてきた動き。
もう一つ好循環という意味でまだかなと思うのは、賃金は上がってきており財価格への波及は進んでいるが、サービス価格への波及が思ったほどではない点。
関税の不確実性が高い中で、利上げの判断はできるのか?
程度の問題。ある程度固まってもその後変更されるリスクは常にあるが、それでも90日の猶予期間である程度不確実は低下すると考えている。
トランプ関税をめぐる経済の混乱は日本の金利のターミナルレートにどう影響するか?
インフレ目標には変化はないので自然利子率がどうなるか?ということだが、直接、自然利子率に大きな影響があるとはなかなか言いにくい。
結論はすぐには出せない。
基調的物価上昇が足踏みするとのことだが、これが足踏みではなく緩やかに下がっていくリスクはあるのか?
あり得る。
企業収益が関税で下押しされるなかで、企業がコストカット型の行動に戻る傾向を示し始める場合に起こり得る。
関税をめぐる不確実性が思ったより早く解消され、利上げを急ぐケースもあるのか?
なんらかの理由で関税を低い水準にすることが起こった場合は起こり得る。
基調的物価上昇率が伸び悩む見通しのなかで、利上げをするとしたら、どういう理屈でやるものなのか?
基調的物価上昇率が伸び悩む中で、無理に利上げをすることは考えていない。
ただ、足元で伸び悩んでいても、その先に色々な条件が重なってまた上がりだして2に到達する可能性が高まれば利上げをする判断はある。
まとめ
今回はとりあえず関税の不確実性が高いってことで、見通しを下方修正してるのでタカ派には感じられなかったですね。
今回は取り急ぎ以上です!
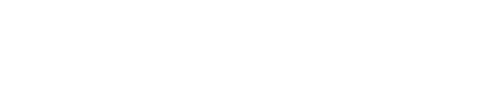
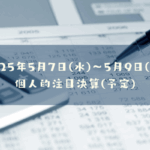
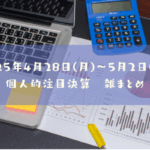
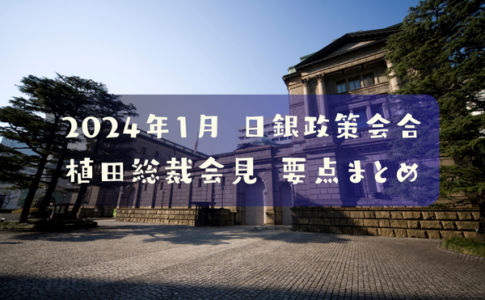









・米国の関税政策をめぐる不確実性は高い
・実質GDPの成長率は2025年度を0.5%(前回1月は1.1%)、26年度を0.7%(同1.0%)にそれぞれ下方修正
・CPI上昇率は25年度は2.2%(同2.4%)、26年度は1.7%(同2.0%)に下方修正
・物価安定目標が概ね整合的な水準で推移するのは見通し期間の後半(26年度後半~27年度?)想定
・見通し期間内に基調的物価上昇率が整合的水準まで高まるという見通しはこれまでと変わっていない